現代の飲食業界において、効率的で高品質な厨房機器は成功の鍵となります。
しかし、市場には数多くの厨房機器メーカーが存在し、どのメーカーを選ぶべきか迷ってしまうことも少なくありません。
本記事では、厨房機器メーカーを選ぶ際に押さえておきたい重要なポイントを厨房機器メーカーの社長が徹底解説します。
この記事では「可能な限り安くてきれいで使いやすい厨房機器選びの情報が知りたい!!」という方向けに記載しております。
ちなみに、

厨房機器の耐用年数は知っているから早く安く借りる方法を教えて!!
という方はサブスクキッチンをご覧ください。



初期費用を抑えて最新のスチコンや厨房機器を使用できるようなサービスです!
\ 初期費用を格段に安く最新機器を使用できる!! /
耐用年数ってなに?


飲食店経営において、厨房設備や家具、家電などの資産が有効活用できる期間を表すのが耐用年数です。
国税庁は、事業に欠かせない機器や設備、備品などの一部は、経年とともに価値が減少すると規定しています。
これにより、一定期間内に資産の本来の価値が減少する資産を「減価償却資産」と称します。耐用年数は、減価償却資産が減価償却を行うことができる期間を示します。国税庁のウェブサイトには、各設備の耐用年数が掲載されており、簡単に詳細を確認できます。
厨房機器の減価償却とは?


減価償却は、長期にわたり使用される資産の取得費用を、その資産が持つ耐用年数に応じて分割し経費として計上する会計手法です。例えば、飲食店で30万円で購入した電気冷蔵庫は、6年間で均等割りして経費計上する必要があります。
対象となるのは経年劣化が見込まれる高額な資産であり、飲食店では主に厨房機器や調理器具が該当します。それに対し、高額でありながら経年劣化しない資産は減価償却の対象外となるでしょう。
また、年度末にはこれらの資産を店の資産として取り扱うか、売却を検討する必要があります。
減価償却費はどうやって計算する?
耐用年数を利用した減価償却費の計算方法は以下のとおりです。
「購入費用÷耐用年数=1年あたりの減価償却費」(今回は定額法をご紹介致します)
イメージとしては、一括の計上ではなく、耐用年数に基づき費用を分割して計上する形です。製品ごとには規定された耐用年数があるため、購入前に必ず確認してから取引を行うようにしましょう。



減価償却を気にせず厨房機器を使いたいという方はサブスクキッチンをチェック!
\ 初期費用を格段に安く最新機器を使用できる!! /
耐用年数はどのように決められる?


コピー機という同じカテゴリでも、メーカーや種類、性質、使用方法によって使用可能な期間が異なります。そのため、自分の主観で耐用年数を決めることはできません。耐用年数は、国税庁が法的に定めています。確定申告用サイト内の国税庁の耐用年数表を参照すれば、厨房設備関連のアイテムについての情報を一部確認できます。
国税庁が定めている厨房設備の耐用年数
こちらでは、飲食店において一般的な厨房機器の耐用年数をご紹介します。
| 電気冷蔵庫・業務用冷蔵庫 | 6年 |
| コールドテーブル | 6年 |
| ガスフライヤー | 6年 |
| 冷蔵ショーケース | 6年 |
| 食器棚 | 8年 |
| 製氷機 | 6年 |
| エアコン | 6~15年 |
| シンク・流し台 | 5年 |
| テーブル(主として金属製のもの) | 15年 |
主要商品の一部の寿命について紹介しましたが、詳細は国税庁のウェブサイト確認することが可能です。このように2年から8年の幅がありますが、通常、飲食店で使用されるキッチン機器は、法定的に8年と規定されています。
使用している機器がどちらに当てはまるかによって、耐用年数が異なるので、ご注意ください。
あくまで上の図は一般例のため、詳しい情報は専門家へお問い合わせください。
厨房設備を買い替えするタイミング


厨房設備は、耐用年数を経過した際以外に、設備の故障や事業の節目などで新調することがお薦めされます。ここで、厨房設備を更新する最適なタイミングをご紹介します。
①目安の耐用年数を経過したタイミング
厨房設備の耐用年数は、通常6〜8年程度です。設備を更新する際、耐用年数がかなり過ぎた古いものは、売却価値が望めない場合もあります。売却できずに廃棄する場合は、追加の廃棄費用も必要となります。効率的な厨房設備の更新を考える際には、耐用年数を1つの目安として検討しましょう。
②厨房設備が故障したタイミング
厨房設備の故障は、買い換えの目安となります。
設備の製造から時間が経過している場合、修理を依頼しても交換可能な部品がないため、拒否される可能性があります。大規模な修理が必要な場合、営業停止の可能性もあります。飲食店の営業に支障をきたさないためには、故障時のメーカー対応期間などを事前に確認することが重要です。
さらに、厨房設備が故障する前の兆候がある場合は、早めの買い替えを検討しましょう。
たとえば、冷蔵庫が十分に冷やせない、オーブンの電源が不安定などです。
③事業の拡大・変更を検討しているタイミング
飲食店の展開や業態の変更時には、厨房設備の刷新が重要なタイミングです。施設や業務内容に不適合な調理設備は、作業効率の低下や業務の乱れにつながります。業務を効率的に遂行し、顧客獲得に向けても設備の更新が勧められます。
そして、居酒屋からカフェに転換する際などでも、古い厨房設備の再利用には限界があります。



飲食店を展開したいけど、新しく厨房機器を揃えるとなると購入にかかる費用が気になります…。



初期費用不要で、必要な期間の利用が可能な業務用厨房機器のサブスクリプションサービスがございます!
ご利用期間が終了しても、ご希望の場合は延長も可能です!
\ 初期費用を格段に安く最新機器を使用できる!! /
厨房機器の耐用年数での注意点


ここでは厨房機器の耐用年数での注意点について解説していきます。
注意点①配管の耐用年数に気をつける
減価償却費を検討する際、多くの場合、厨房機器に焦点を当てがちですが、飲食店経営にとって重要なのは、給排水設備という必須の設備にも耐用年数を考慮して減価償却費を算出することです。
ポンプや配管などの給排水設備は、厨房機器とは異なり、建物に付属する設備として分類されます。配管の耐用年数は15年です。
注意点②減価償却の特例に気をつける
全てのアイテムを減価償却する必要はありません。
青色申告をしている個人事業主の方は、1つあたり30万円未満のアイテムについては、「少額減価償却資産の特例」を活用すれば、全額を一括で経費として計上できます。収益が多い年には、減価償却をしないで一括で経費として計上し、利益を減らして節税したり、売上が少ない年には30万円未満でも減価償却をしてコストを分散させるなど、選択肢があります。
しかし、ご注意いただきたいのは、一旦減価償却か特例を選択したら、後から変更することはできません。減価償却を選択し、コストを分散して計上していた場合、翌年に残りを一括で計上することも不可能です。
注意点③中古の厨房機器に気をつける
厨房機器を新規に購入しようとすると、相当な費用を見込まなければなりません。その費用を回収するのには時間がかかることを考えると、負担に感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、中古の厨房機器ならば価格は異なりますが、一般的に新品の5分の1程度の金額で入手できるため、売上が伸び悩んでも利益が損なわれることはありません。
勿論、中古の厨房機器には利点ばかりではありません。中古品は以前に使用されていたため、既に劣化が始まっており、新品と比べて故障の可能性が高くなります。そのリスクを含めて価格が抑えられているため、新品と中古のどちらを選ぶかはお客様次第であり、一概にどちらが良いとは言えません。
厨房機器の耐用年数を気にしたくないならサブスクキッチンがオススメ!!
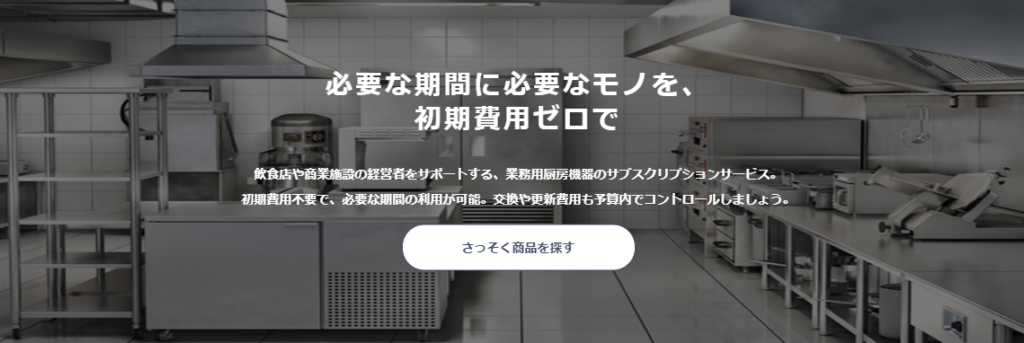
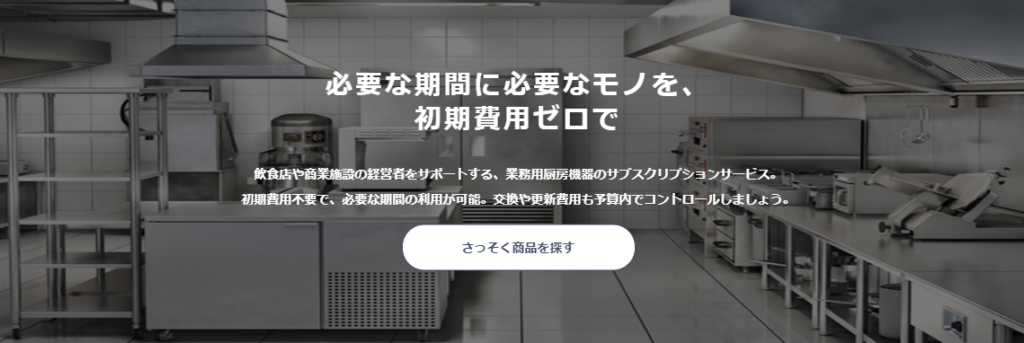
厨房機器の耐用年数を気にしたくない人はサブスクキッチンがオススメです。
サブスクキッチンは、業界内でも優れた品揃えを誇るとともに、リースとは異なり、長期間の契約が可能です。
新品の機器を利用できる点も、一般的なレンタルとの大きな違いです。加えて、保守・修繕についても、サービスが提供されているため、厨房機器を購入する必要性はありません。
初期費用が0円であり、月々の定額制により最新の機器を手に入れることができます。



初期費用をなるべく抑えて起業したい人や最新機種が欲しい人は是非ご覧ください!
ご利用期間が終了しても、ご希望の場合は延長も可能です!
\ 初期費用を格段に安く最新機器を使用できる!! /
まとめ
厨房設備の耐用年数は、その設備が価値を維持する期間を示します。各種厨房設備や備品には、それぞれ耐用年数が規定されています。耐用年数が終了しても、直ちに設備が使用不能になるわけではありません。
ただし、耐用年数を基準にして、適切なタイミングで新しい厨房設備に更新することで、減価償却による節税効果が期待できるでしょう。建物や内装などの老朽化がみられる場合は、新規店舗への移転も顧客獲得の観点から有効です。










コメント
コメント一覧 (1件)
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.